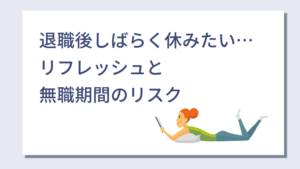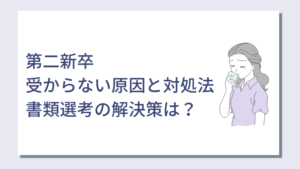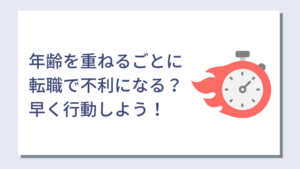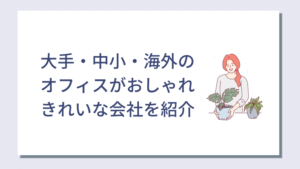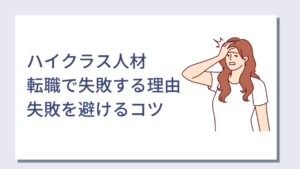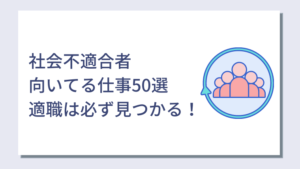「会社を辞めたら、まず何をすればいいのか?」
会社を辞める前はバタバタと忙しく、そこまで考えている余裕がなかったかもしれません。そして、今現在も辞めた後の疲労感で行動に移すのが億劫になっているかもしれませんね。退職というのは、とても大きなエネルギーがいるものですから…。
とは言え、退職して失業期間に入ったら、やっておかなくてはいけない手続きがあります。それをしっかりと把握して今のうちから行動していけば、スムーズに次のステップを踏んでいけるはずです。
- 転職先が決まっていない状態で辞めてしまった
- 会社を辞めてしばらくのんびりしたい
- 失業保険をもらいながらじっくり転職活動したい
という人は、各種手続きが必要になりますから、退職後にやるべき手続きをしっかりと確認して、後で慌てないようにしましょう!
失業保険の手続き
失業保険の手続きについて、ポイントをまとめました。
- 失業保険の手続きの方法は?
- 失業保険はいつからもらえる?
- 失業保険はどのくらいの期間、いくらもらえる?
- 再就職手当とは?
失業保険の手続きの方法は?
会社を辞めたあとに頼りになるのが「失業保険」です。こちらの手続きは、どの手続きよりも最優先でおこなうべきでしょう。手続きが遅れた分だけ支給も遅れますから、早めに手続きをおこなってください。
失業保険を受給するためには、自分の住所または居所を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。申し込みには、以下のものが必要になります。
- 離職票(退職した会社から受け取る)
- 雇用保険被保険者証(退職した会社から受け取る)
- 印鑑
- 住所を確認できるもの(住民票や運転免許証など)
- 顔写真2枚(縦3cm、横2.5cm程度の正面上半身のもの)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
- 通帳
離職票は、退職から10日前後で会社から送られてくる書類です。自宅に届くまでの目安としては、2週間ほどだと考えておいてださい。
もし2週間以上経っても離職票が送られてこない場合は、会社に直接電話で連絡して送ってもらいます。「連絡したにもかかわらず、会社が離職票を送ってくれない」など悪質な場合は、ハローワークに連絡することで離職票の再発行をしてもらうことができます。
上記必要なものを全て揃えて、あなたの住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みをすると、ハローワークから説明会の日時の指定をされます。
説明会では、失業保険の受給方法や認定日などの説明があり、「受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡されますので必ず出席するようにしてください。このときに第1回目の「失業認定日」の指定があります。
指定された日時にハローワークへ行く必要があるから、指定の日時を忘れないようにしましょう。

失業保険はいつからもらえる?
「失業認定日」には必ずハローワークに行くようにしてください。出席しないと給付が受けられなくなることもあるので、注意が必要です。
急に出席できなくなったときには、事前に必ずハローワークに連絡をいれましょう。最初の失業認定日は、ハローワークに書類を申請した日から原則4週間後です。その後も4週間ごとの失業認定日が続いていきます。
その4週間に、2回以上(最初の認定日までは1回以上)求職活動の実績がないと、失業保険はもらえません。失業認定が認められると、1週間ほどで指定の口座に失業保険が振り込まれます。
失業保険の支給開始日は、退職の理由によって異なります。
自己都合退職(自分の都合で退職した場合)には、求職の申し込みから7日間の待機期間のあと3ヶ月間の給付制限期間があります。なので、給付が開始されるのは1週間+3ヶ月後からということになります(実際に支払われるのは、求職の申し込みから約4ヶ月後)。
会社の倒産やリストラなど、会社都合で退職した場合には、3ヶ月の待機期間はありません。求職の申し込みから7日間の待機期間の後、8日目から支給が開始されます(実際に支払われるのは、求職の申し込みから約1ヵ月後)。
失業保険はどのくらいの期間、いくらもらえる?
雇用保険の失業保険の金額は、退職時の年齢と退職前6ヶ月の給料、勤続年数(被保険者であった期間)によって異なりますが、1回分の支給で前職での月収のおよそ5~8割程度です。大体、前職の6割くらいと思っておけばいいでしょう。
給付金は1日あたりの支給額(基本手当日額)で計算されます。基本手当日額は、退職までの6ヶ月の賃金(賞与や退職金、特別手当を除く)の合計を180で割り、その金額に応じた給付率を乗じて決められます。
※平成30年8月2日~。詳しくはハローワークに問い合わせをしてください。
◆基本手当日額の上限◆
| 30歳未満 | 6,750円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,495円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,250円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,083円 |
また、失業保険の支給が受けられる日数は(所定給付日数)は、勤続年数と、「自分の意思で会社を辞めた人(自己都合)、または定年退職者」か「倒産・解雇などで再就職の準備をする時間に余裕がなく離職せざるを得なかった人(会社都合)」かで違ってきます。
◆失業保険の給付日数◆
| 対象者 | 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 自己都合退職者 | 65歳未満の場合 | – | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 会社都合退職者(倒産や解雇等) ・特定受給資格者 ・特定理由離職者 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 同上 | 30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 同上 | 35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 同上 | 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 同上 | 60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 65歳以上(高年齢求職者給付金) | 65歳以上 | 30日 | 50日 | 50日 | 50日 | 50日 |
| 65歳以上(高年齢求職者給付金) | 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 就職困難者 | 45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
基本手当の支給を受けることのできる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。これを過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていたとしても給付金はもらえません。申し込みは遅れないように注意しましょう。
◆まとめ◆
失業保険(基本手当)の合計額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
※基本手当日額とは・・・失業保険で受給できる1日あたりの金額のこと。
基本手当日額=賃金日額×50~80%(60歳以上については45~80%)
賃金日額=退職直前6ヶ月の給与総額÷180(30日×6ヶ月)

再就職手当とは?
雇用保険の受給中に再就職先が決まった場合には、失業保険の給付はストップします。ですが、早期に再就職した場合には、残っている給付日数分の失業保険のうちから、一定の割合をもらうことができます。以下の受給要件をクリアしていれば、再就職手当が支給されます。
- 7日間の待機期間が過ぎた後に再就職、または事業を開始したこと
- 所定給付日数が3分の1かつ45日以上残っている
- 退職した会社に再び再就職したり、グループ企業でないこと
- 失業保険受給の手続き前に再就職が決定していたものでないもの
- 3ヶ月の給付制限がある(自己都合退職等)場合、待機期間満了後1ヶ月以内に就職した先については、ハローワークの紹介であること
- 再就職先で1年間以上雇用されることが確実になっていること
- 再就職手当の支給決定日までに離職していないこと
- 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
再就職手当の支給額は、基本手当日額に基本手当の残日数をかけた金額をもとに、残日数に応じた割合が支給される計算になります。この割合は、
・残日数が3分の2以上ある場合は70%
・残日数が3分の1以上ある場合は60%
です。つまり、早く再就職をするほど受給額が増えるということになります。
また、再就職手当の支給対象となる就業形態以外で就職した場合(アルバイトなど常用雇用以外の形態)には、「就業手当」(支給残日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合)が支給されます。再就職が決まったら、すぐにハローワークに連絡し、確認しましょう。
ちなみに、会社を辞めた時点で転職先が決まっている場合は、転職先の会社に「雇用保険被保険証」を提出すればOKです。
健康保険の手続き|健康保険には必ず加入しよう
会社を辞めると、今まで加入していた社会保険も、退職日翌日から失効になります。つまり、会社を辞めると自動的に「健康保険」から抜けるということです。
そこで、以下の3つの選択肢の中からどれかを選んで、健康保険に加入することになります。
- 国民健康保険に加入するか
- 「任意継続制度」を利用する
- 家族の扶養に入る
もしくは、家族(配偶者や親など)の加入している社会保険に扶養親族として加入する方法もあります。
まずは家族の「被扶養者」になれないかを確認しましょう。「被扶養者」になることができれば、健康保険料の負担がないのでお得です。ただし、失業保険をもらっていると、原則として「被扶養者」にはなれないので注意してください。
ですので、失業保険を受け取るつもりの人は「任意継続」「国民健康保険」のどちらかを選択することになります。ここで気になるのは、どちらの方法を選んだ方が安いのか?ということですよね。これは人によって違ってきます。
国民健康保険の保険料は自分が住んでいる市区町村役場で、健康保険の保険料は自分が住んでいる地域を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合の事務所)で聞くことができます。
一般的には前職の給料が高いほど、国民健康保険料は高くなります。したがって、年収が高めだった人は任意継続のほうがお得になる傾向があるようです。
◆任意継続被保険者制度◆
退職した会社で加入していた健康保険に、引き続き加入できる制度です。健康保険の加入期間が退職日まで継続して2ヶ月以上あれば、この制度を利用できます。ただし、加入期間は、退職してから原則として2年間までです。
保険料は、在職中は2分の1を会社が負担していましたが、この制度では全額自己負担になります。これまでの保険料の倍になる人がほとんどです。手続きは、自分の居住地を管轄する社会保険事務所、あるいは会社が入っている健康保険組合の事務所で行います。
手続きのときに必要なものは、住民票、印鑑、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書(社会保険事務所、または健康保険組合の事務所にあります。これには退職前の保険証の記号・番号を記入するので、退職するとき、保険証を会社に返す前にメモしておきましょう)に、保険料(1~2ヶ月分)です。
手続きは、退職日の翌日から20日以内にしなけないので注意が必要です。1日でも遅れると受け付けてもらえません。
◆国民健康保険◆
国民健康保険の加入資格は特にありません。他の健康保険に加入していない人が対象となります。保険料は、前年の収入と市区町村によって異なります。
手続きは、自分の住所を管轄する役所に行って、国民健康保険課などの担当窓口で行います。手続きには、印鑑と地域によっては前の会社から受け取った「健康保険資格喪失証明書」や「源泉徴収票」が必要になります。
もし証明書を受け取っていなかったら、前の会社に請求するか、会社の住所を管轄する社会保険事務所に行けば手に入れることができます(ただし、配偶者がいる人は手続き方法が異なる場合があります。詳しくは市区町村役場に問合わせましょう)。
手続きが済むと、国民健康保険被保険者証を発行してくれます。保険料の納付方法は、役所から納入通知書が送られてくるので、この通知書にしたがって役所の担当窓口か指定された金融機関で納めます。
再就職して会社の健康保険に加入したら、国民健康保険の被保険者証、会社の被保険者証、印鑑を持参して、役所で資格喪失の手続きをします。
また国民健康保険で病院に通院している場合は、再就職先の新しい被保険者証を提示して保険の種類が変更したことを伝えましょう。
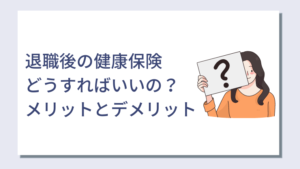
国民年金の手続き
ここからは、国民年金の手続きについて見ていきましょう。
- 年金の受給資格を失う可能性もある
- 手続き方法
年金の受給資格を失う可能性もある
会社を辞めると、自動的に厚生年金から脱退したことになります。すぐ次の会社に入社する場合は、その会社で厚生年金に加入しますから問題ありませんが、失業期間がある場合には国民年金への種別変更手続きが必要です。
国民年金への変更を忘れてしまうと、年金に加入していないことになり、未納のまま放置しておくと督促のハガキが送られてきてしまいます。
原則、退職してから14日以内に、国民年金の手続きをしなければいけません。将来年金を受け取るには、「保険料を納めた期間が10年以上」という受給条件があります。
つまり、失業中に年金の種別変更手続きを行わず、保険料を払わないでいると年金の受給資格がなくなってしまうこともありえます。
手続き方法
国民年金への種別変更手続きは、退職してから14日以内に自分の住民票がある役所で行います。持参するものは、
- 年金手帳
- 身分証明書
- 印鑑
になります。「年金手帳」は、自宅に保管している場合もあれば、前職の会社に預けていて会社を辞める際に会社から受け取る場合もあります。
「年金手帳がない…どこにいったか分からない」という人もいるかもしれません。そのような場合は、社会保険事務所で再発行してもらえるので安心してくださいね。
保険料を納めるのが経済的に困難な場合は、免除してもらう方法もあります。役所で免除申請書をもらい、現在収入がないなどの経済状況と免除の希望期間を記入して提出し、この申請が受理されれば、保険料が免除されます。免除の種類は、
- 4分の1免除
- 半額免除
- 4分の3免除
- 全額免除
があります。免除の申請をした場合、5年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができ、追納した分は、年金額に反映されます。
税金の手続き
税金の手続きについて、以下のポイントをおさえておきましょう。
- 所得税の還付手続き
- 退職金にかかる税金
- 住民税の納付方法
所得税の還付手続き
給料から天引きされる税金は「所得税」と「住民税」です。所得税は、源泉徴収税額表に基づいて天引きされますが、源泉徴収された税額の合計と本来の年間給与総額に対する年税額とは、通常一致しません。この不一致を、1年に一度精算するシステムが、「年末調整」です。
年末調整で、たいていの場合は納めすぎた所得税を還付してもらえます。
ただし、会社を辞めてしまうと会社は退職した人の年末調整をしてくれないため、次のいずれかの方法で還付を受けることになります。
◆退職した年内に再就職した場合◆
新しい会社に、退職した会社からもらった源泉徴収票を提出すれば、会社が年末調整をしてくれます。その際、生命保険、損害保険、住宅ローンなど所得税の控除対象になる支出があれば、その控除証明書や領収書もいっしょに提出します。
◆退職した年内に再就職しなかった場合◆
この場合は、自分で確定申告を行う必要があります。自分の住所を管轄する税務署で申告書をもらい、必要事項を記入して提出します。申告書には、退職した会社からもらった源泉徴収票を添付しなければいけません。また、年末調整と同じように控除対象の支出があれば控除証明書や領収書も添付します。
確定申告の時期は、2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。期間中は、税務署には確定申告のための相談コーナーが設けられているので、わからないことがあったら聞けば教えてくれます。
ちなみに今は、ウェブ上で申告書を作成したり、インターネット経由で確定申告を行うこともできます。パソコンに慣れている人であれば、それらの手段を使えば確定申告の手続きはさらに手軽になるので、気軽に確定申告に取り組んでみてください。
退職金にかかる税金
退職金にも、税金がかかってきます。ただし、一時的な収入なので、給与所得とは分離して課税する分離課税方式で税額が決まります。課税対象となる金額は、退職金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1です。退職所得控除額は、勤続年数に応じて決まります。
勤続年数が20年以下の場合、控除額の算出方法は、40万円×勤続年数となります。勤続年数が20年を超えると、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。たとえば、勤続年数が6年の場合、40万円×6年=240万円となり、退職金が240万円以下なら非課税です。
住民税の納付方法
住民税は、ある年の所得に対する税額を、その翌年6月から翌々年5月にかけて納付する後払いのシステムになっています。会社員は、住民税を毎月の給与から天引きされますが、退職した場合は、何月に退職するかによって、退職した後の住民税の納付方法が変わってきます。
◆1月から5月の間に退職した場合◆
残りの住民税は会社が一括して徴収します。たとえば2月に退職すると、残りの3月から5月の分も退職するときに徴収されます。
◆6月から12月の間に退職した場合◆
納付方法は2通りあり、どちらかを選ぶことができます。ひとつは、退職するときに会社に一括で支払う方法です。6月に退職してこの方法を選択すると、翌年5月までの1年分の住民税をまとめて支払うことになります。
もうひとつの方法は、役所に分割払いで納付する方法です。この方法を選ぶと、退職した後、役所から納税通知書が送られてくるので、通知に従って納付します。
退職時に、いずれの方法を選ぶか会社を通じて役所に届けを出してもらいます。また、退職した年の所得に対する住民税については、就職していれば給与から天引きされます。
失業中の場合は、退職年の翌年6月から翌々年5月にかけて納付することになります。役所から送られてくる納税通知書に従って、納付しましょう。
会社を辞めた後の手続きはめんどくさいですが…
会社を辞めると、色々な手続きを自分でしなければいけないので「めんどくさい」と感じる人もいるでしょうね。本音を言えば、会社を辞めたら「もう何もしたくない」という感じになるかもしれませんが、重い腰をあげてひとつひとつ手続きを済ませていきましょう。
会社を辞めた後というのは、本当に何もしたくなくなりますよね。今まで忙しく働いてきた分、その反動がとても大きいのだと思います。その気持ちはよく分かります。
失業保険は必ず手続きを済ませよう
会社を辞めるということは、決してポジティブな理由で辞めた人ばかりではなく、ネガティブな理由で辞める人も多いと思います。実際私も、会社の人間関係がイヤになり逃げるように会社を辞めたひとりです。
私も会社を辞めてからは、何もやる気がおきずに毎日ぼんやり過ごしていました。「いろんな手続きをやらないといけないな…」と頭では考えていましたが、体が動きません。結局、すべてを後回しにして、退職してから半年ほど経ってからやっと失業保険の手続きに行きました。
そのときに思ったのは、「もっと早く手続きをしておけばよかった」ということです。会社を辞めてから何も行動しなかったため、貯金も底を突きかけていました。会社を辞めた直後に手続きを済ませておけば、50万円ほどの失業保険をもらえた計算になります。
ある程度休んだら行動を開始する
会社を辞めたら、次の仕事についても考えていかなければいけませんよね。特に、まだ転職先が決まっていないなら、本来なら焦らなければいけないはずですが、何もやる気がおきないという人もいるかと思います。
しかし、休めば休むほど、転職活動をするのが難しくなってきます。体が「怠けモード」に突入してしまうのですね。そうなると、外に出るのも億劫になり、家でテレビをみたり、ネットサーフィンで一日が終わってしまうなんてこともあるでしょう。
そして、いつの間にか失業保険の期間も切れてしまい、生活費のためにアルバイトを始めて、そのままズルズルと非正規社員の道へ…。
脅すわけではありませんが、休む期間は区切りをつけて、「ある程度休んだら行動を開始する」と決めておいた方が良いでしょう。1週間旅行に行って、そのあとから転職活動を始めるということでもいいと思います。
休む期間は1週間~2週間くらいがいいのではないでしょうか。数ヶ月単位で休んでしまうと、重い腰がますます重くなってしまいますから。
いきなりフルスピードで転職活動は難しいですから、1週間ほど休んだら、慣らし運転をしながら徐々に転職活動のスピードを上げていきましょう。転職活動の始めの一歩ですが、ハローワークを利用してもいいですし、転職サイトを眺めてみるのもいいです。
最もおすすめなのは、転職エージェントですね。転職エージェントのアドバイザーは、さまざまな転職情報を持っていますから、しゃべるだけでも参考になることが多いと思いますよ。