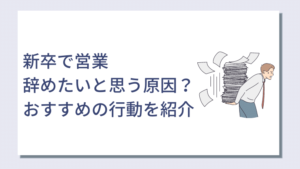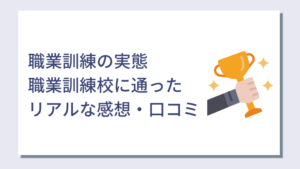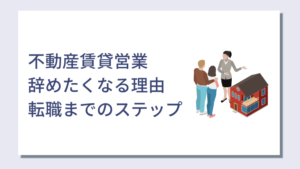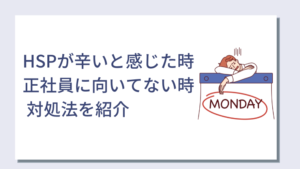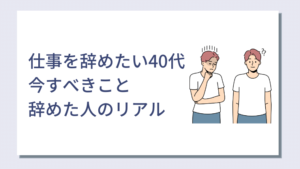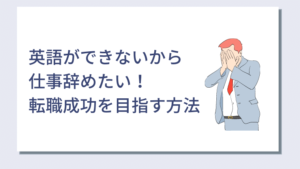「契約社員」は全国に100万人~200万人いると言われています。
また、労働者派遣法の度重なる改正によって、いまでは多種多様な職種で派遣社員が働くことが認められるようになっています。
このように、昨今では「契約社員」「派遣社員」として働く人がとても多いです。では、「契約社員」や「派遣社員」が失業したときに、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
失業したときに頼りになるのが、失業保険の存在です。
今回の記事では、「契約社員」「派遣社員」でも、失業保険をしっかりともらう方法を詳しく解説します。
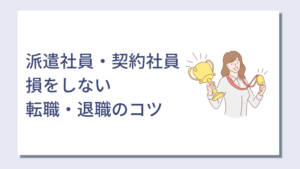
「契約社員」が失業保険をしっかりもらう方法
契約社員が失業保険をもらう際は、以下のポイントをおさえておきましょう。
- 短期契約の繰り返しは「正社員扱い」
- 労働者側からは1年経過後は自由に辞められる
- 「週20時間」「1年以上」なら失業保険はもらえる
短期契約の繰り返しは「正社員扱い」
契約社員の契約期間は、以前は一年を超える期間は設定することができませんでしたが、2013年度の労働基準法改正で、原則として最長3年まで可能になりました。
期間が長くなったので、働く人にとって有利になったように思われますが、会社にとっては一定期間の経過で労働契約が自動的に終了になるため、正社員で雇うよりもリスクが少なくてすみます。
正社員に会社側から一方的に辞めてもらう場合は、「解雇理由に合理的理由が必要となる」などさまざまな規制があります。
期間契約で働く人にとって、最大の関心事は、この会社でいつまで働けるのか、つまり、「契約期間の延長はあるのか」ということでしょう。
契約社員の場合は、その後の生活の見通しを考えなければならないことから、次の基準が設けられています。まず、企業側は雇い入れの時点で、契約の更新はあるのか、その場合の基準はどうなっているのかを明示しなければいけません。
さらに、更新がある場合で、次は更新がない場合には、契約期間満了の少なくとも30日前までに、その旨を通知することになっています。
更新しない場合の理由を請求すれば、教えてもらえる、ということになっています。もっとも、これらの制度は、基準として設けられているだけで、違反したからと言って、延長してもらえるわけではありません。
しかし、次のようなケースは、契約社員にも勝ち目があります。会社が短期の契約を繰り返すパターンです。企業としては、後腐れなく縁切りできる期間雇用を”活用”して短期の契約を何度も更新した方が得です。
ところが、このようなケースは、制度を悪用しているものとして、労働基準監督署も問題にします。3回以上繰り返し期間契約した場合には、もはや期間の定めがない「正社員」と同様の保護を受けられるという判決も出てきます。

労働者側からは1年経過後は自由に辞められる
期間雇用は、会社に有利な制度であることから、改正で次のような仕組みが加わりました。
期間雇用の場合は、会社も労働者も期間内は一方的に契約を解約することはできません。しかし、1年を超える期間を設定した場合は、労働者側からは自由に辞めることができるようになったのです。
例えば、2年の契約で働いた場合、2年間拘束されるわけですが、1年を経過した日以後は労働者の側から自由に辞めることができます。
「週20時間」「1年以上」なら失業保険はもらえる
契約期間満了に伴う”クビ”の場合でも、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?それは、勤務形態によります。
正社員と同様の時間で働くのであれば、契約期間に関係なく雇用保険に入れます。また、パートのような短時間で働く場合は、「1週間で20時間以上働き」かつ、「1年以上働く見込みがある場合」に限って雇用保険に入れます。
契約社員には、A社に5ヶ月、B社に8ヶ月といったように細切れに働くケースもあります。このような場合も、契約社員は1年以内に再就職すれば、雇用保険の被保険者期間が通算され、2回めの会社を辞めても失業保険はもらうことができます。
ですから、前職での離職票を保管しておくことが重要になります。契約社員が期間満了となり会社を辞めた場合は、基本的には一般受給資格者となりますが、3ヶ月の「給付制限」はありません。
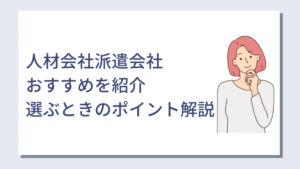
「派遣社員」が失業保険をもらえる条件
ここからは、派遣社員が失業保険をもらう際のポイントを見ていきましょう。
- 「派遣切り」にはこう対応する
- 派遣社員が失業保険をもらうためには
- 派遣社員も「特定受給資格者」になれる
「派遣切り」にはこう対応する
会社が、派遣社員を労働力の調整弁として活用し、景気が悪くなったら「ポイ捨て」することが横行し、「派遣切り」という言葉まで生まれる事態になりました。
契約社員や派遣・パートなどの非正規雇用社員の不安定な雇用状況は、社会問題ともなっています。
ここで、派遣社員の立場について触れておきましょう。派遣社員は、派遣会社(派遣元)と労働契約を結び、その契約に基づいて、派遣先に派遣されています。
つまり、派遣先とは、労働契約関係は成立していないのです。したがって、「派遣先」が業績不振で派遣会社に対して派遣契約を中途で打ち切った(これがいわゆる”派遣切り”)としても、派遣社員は何も主張することができません。
派遣社員は、派遣元に対して労働契約上の主張をすることができます。
例えば、3ヶ月の派遣契約で派遣先で働いていたのに、派遣先の業績悪化によって1ヵ月で打ち切りになった場合には、派遣元である派遣会社に対して、別の仕事を用意してもらうか、用意できない場合には、「休業手当」という労働基準法上のしくみで一定額(働いてきた期間の賃金の60%に相当する額)を請求できます。
また、派遣元は、新しい派遣先が見つからないという理由で「解雇」もできません。解雇には、法律上の「正当な理由」が必要になるからです。
新しい派遣先が見つからないというのは、よほどの理由がない限り「正当な理由」には該当しません。最悪、解雇ということになったとしても、「解雇予告手当」という30日分の賃金を請求することができます。
派遣労働者のこのような権利を無視して、派遣元が一方的な解雇をしてきた場合には、ユニオンや労働基準監督署に相談するなどして、対抗しましょう。
派遣社員が失業保険をもらうためには
派遣社員であっても、雇用保険への加入が義務付けられています。ただし、正社員と異なり、一定の条件付きとなります。その条件とは、
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 反復継続して1年以上、派遣で働く者であること
という2つです。もし、派遣社員でこの条件に該当しているにもかかわらず、雇用保険に未加入の場合には、ハローワークに「確認の請求」をすれば2年前まで遡って、雇用保険の加入を認めてくれる制度があります。
派遣社員も「特定受給資格者」になれる
派遣社員の場合、特定受給資格者になれる基準は、正社員や契約社員と少し違います。
「派遣先企業」と「派遣元企業(派遣会社)」の間の契約満了により仕事を終えたあと、本人が今後も同じ派遣会社からの仕事を希望していて、派遣会社が次の就業先を1ヵ月ほど探しているにもかかわらず、見つからない時に、特定受給資格者になれるのです。
派遣先から切られたからといって、すぐに派遣会社に退職願いを出すと、「自己都合」扱いで一般受給資格者になってしまうので注意しましょう。
ただし、ハローワークでは、現在の雇用情勢を踏まえて、派遣会社が次の就業先を紹介できないことが明らかな場合には、1ヵ月待たずとも特定受給資格者にしてくれるケースがあります。
さいごに
「契約社員」や「派遣社員」が失業した際に、頼りになるのが失業保険の存在です。今回の記事を参考にして、しっかりと失業保険を受け取りましょう。
また、失業中の転職活動では、「契約社員」「派遣社員」ではなく、正社員を目指す努力を怠らないようにすることが大切です。
正社員として雇用される努力を後回しにしてしまうと、年齢が増すにつれて、正社員採用どころか、就職すること自体が厳しいものとなってしまいます。
自分自身のライフワークやキャリアの目標を踏まえて雇用形態を選ぶべきですが、まずは正社員をめざす努力をするのが賢い選択です。